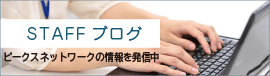ピークスネットワークの就労支援の特徴
PEAKS六甲

神戸大学の最寄駅であるJR六甲道駅前にあります。
改札口を出ると、雨の日でもそのまま傘不要で、施設が入居しているウェルブ六甲道2番街に行けます。ここは1階が銀行・食堂街、2階が店舗・カルチャースクール、3階が各種医療施設、4~6階が企業オフィスでそれ以上30階までが住宅という複合施設で当施設は5階にあります。
改札口から所要時間は速ければ1分間。こうした環境の良さは大きく言って2つの効果をもたらせます。
一つは、利用者は施設に通うということではなく会社に出勤しているという実践感覚の中で訓練が受けられること。ビジネスウェアーで鞄を持ち、颯爽と通って来られます。
もう一つは、他の会社で働いている人たちとの関係性が取れること。多くの施設が企業から指摘をされ就職するのは挨拶が何より大事だと、挨拶の練習をするがほとんどは練習のための練習でおわっているのが現状ではないでしょうか。
でも、エレベーターホールで他社の方々と日常的に出会い、「おはようございます」「こんにちは」「お疲れ様」等様々な挨拶を交わしていくと、挨拶って気持ちいいものだという体感をしていきます。この体感をするということが極めて重要で、利用者は挨拶スキルをどんどん向上させていきます。
PEAKS神戸

兵庫県の基幹職安であるハローワーク神戸の東隣のビルにあります。
すぐ近くには労働局もあります。そして、隣室は雇用開発協会です。このビルは兵庫県で長く就労支援に携わっている人にとっては特別な場所で、企業さんをお連れして助成金の申請手続きに何度も来たという思い出を持っておられます。
2箇所目はこのビルしかないという思いが実現できて大変嬉しく思っています。
ハローワークが隣にあるということで、相談や求人検索が非常に便利だということは勿論ですが、ハローワークに相談に来られた企業や大学の職員が紹介されて訪問していただける機会も多く、企業や大学との連携も進んでいっています。

まずは自分を知ることからはじまります。自分を知ることは、自分を変えることではない。今の自分をありのままに、強み、弱みをしっかりと自覚することです。
でも、発達障害の特性だから仕方ないでは済まさず、自分の得意なところで勝負する。それが難しい場合は配慮をしてもらう。そのことをきちっと伝える力をつけていきます。
そのためグループワークを数多く取り入れ、人前で自分の考えを話したり、他者の意見に共感したり、コンセンサスを得る力を仲間とまた職員との共同作業を通して獲得していきます。
その他、自らの体験を下に発達障害の特性を理解し対処方法を学ぶプレゼンテーションや、ネガティブな言葉をポジティブな言葉に置き換える「ネガポ辞典づくり」、「イイトコサガシ」などを通して自己肯定感を高めることを目指しています。
また、朝礼、終礼の司会をはじめ様々な当番を担い達成感や役割を果たす大切さを学んだり、通院等で当番が担えない日の代替を頼む、受けるといった経験を通して、他者との関係性力をつけていきます。

大半の利用者は思いをまとめて話すことに苦手意識があります。それ故、会話を避けてきたし、相談の必要性はわかっていても出来ないでいました。
それが、自分と同じ生きにくさを抱えている集団の中で、ここなら自分のまとまりのない話を拾い上げてくれるという安心感を得て、会話や相談が出来るようになり、その居心地の良さを体感します。また、同じ発達障害という診断を受けてはいるが、個々によって得て不得手は違うことがわかってきます。
この違いが判ることによって、自分を認められるようになります。自分を変えることではない、自分を知ることが大切なのだ、そして強みで勝負出来れば良いが、そうでなくとも配慮してもらえば良いのだということがわかってきます。
人から係わられることを極端に嫌がる人に、すぐにお節介を焼きたがる人がいます。当然、衝突するわけですがそのような環境の中で「あのお節介から逃れるためにはもっと自分をオープンにしなければいけない」と気づき、笑顔が出るようになった利用者もいます。このような例はいくつもあるのです。
職員は福祉を専門的に学んだ者よりも企業の障害者採用担当や大学の学生支援室で実際に障害学生を支援してきた者、ハローワークの専門援助部門で働いていた者、作業療法士、経理担当等多様な人材を配置しています。
このような配置が利用者には極めてシンプルで分かりやすいようです。
期間の満了に伴う安易な就労継続B型への移行をしないために、就労移行支援事業単体で運営しています。
知的、精神障害のある人の人口発生率は2~3%に対して、発達障害のある人は、アメリカとか韓国の統計では、11~12%と言われるようになってきています。
これは、障害とは時代が作り出していく典型を意味します。つまり、増えたのではなく時代環境が目立たせてきたということです。時代は科学技術の進歩による合理化を推進し、ひとり一人にかかる仕事量が急激に増えるとともに、まるでイス取りゲームのように弾かれていく人たちを生み出します。
超高齢化社会を支えていく若い世代が、今のような状況でイス取りゲームから弾かれていく。その中に発達障害という烙印のなかで、生きにくさをかかえて、企業の中に入れない層が数多く存在することが目立ってきています。
この状況が続けば我が国の社会保障制度は崩壊する深刻な課題です。市場万能主義に対抗する概念や思想を見出した実践を行わない限り、私たちは21世紀の超高齢社会を持続的に発展させることはできないのです。
正に、発達障害のある人の就労支援は障害者支援ではなく社会変革という認識を持ち、国民的課題として取り組む意識が必要だと実感しております。